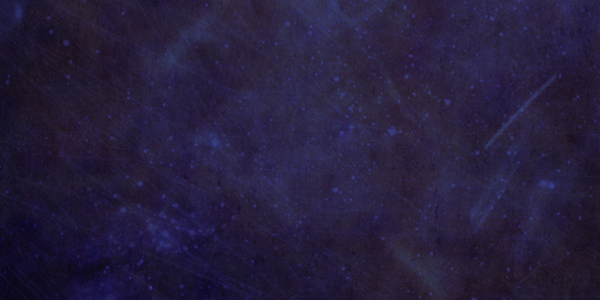先月スカルパを書いたので、今月は現在も活躍するスーパースター、マリオ・ベリーニを書くことになりましたが、彼もまたどれをとりあげようかと悩むほど多くの名品があります。一脚となれば、デザインされたのは1976年とだいぶ後になりますが、革で包んだ「キャブ」でしょう。
マリオ・ベリーニは1935年イタリアのミラノに生まれ、1959年ミラノ工科大学建築科を卒業。ミラノを拠点に活動範囲も建築からインテリア、家具、工業製品と幅広く、1987年ニューヨーク近代美術館での展覧会で大きな評価を得て世界的スターとなる。
初期には工業製品や家具などのプロダクトデザインが多く、オリベッティ社の計算機や電子タイプライターなどが代表作。椅子のデザインも多い。代表的なものを年代順にあげると、FRPのL型のフレームにクッションを載せて構成する「アマンタ、Amanta」(1966)に始まり、クッションを組み合わせて無限に拡大していくシステムを構成した「カマレオンダ、Camaleonda」(1970)、鉄の簡単なフレームを芯に成型したウレタンフォームを布でかぶせてシリーズ展開した「ル・バンボーレ、Le Bambole」(1972)、そして「キャブ、Cab」などがある。
「キャブ」は、スティールのフレームを良質の鞣革で包んだユニークな椅子で20世紀の名品。同じつくり方の肘掛タイプなど数種類がある。
80年代には、ドイツ・ビトラ社(*1)のオフィス用椅子のシリーズ「ベリーニ・コレクション」は「ペルソナ、Persona」、「フィグラ、Figura」「イマゴ、Imago」という三部作からなり、ティール(Dieter Thiel)との共同デザインである。なかでも、「フィグラ」はハイテクでハイタッチの事務用椅子として評判となった。これは当時の傾向である人間工学的視点からのメカニズムを内蔵しながらも布地のカバーを取替え可能として、オフィスにカラフルなファション感覚を持ち込んだ傑作。(*2)照明器具ではアルテミデ社の「アレア、Area」(1974)などがある。
90年以後は建築のプロジェクトに傾注し、イタリアのみならず世界各地におよぶ。家具を含め、いずれも洗練された豊かな造形美がベリーニの特質である。
日本との関わりも多い。ヤマハのカセットレコーダ(1975)はユニークな造形で評判を呼んだし、建築設計では1992年3月にオープンした東京デザインセンター(東京・五反田)があり、このときベリーニも来日し「フォーラム」も開催された。
受賞は黄金コンパス賞のほか世界中で数多くある。また、デザイン活動のほかにも、多くの大学で教鞭をとり、ミラノ・トリエンナーレにもかかわり、雑誌「ドムス」の編集長(1986〜91)も勤めた。
デザイン:マリオ・ベリーニ(Mario Bellini 1935 〜)
製 造:カッシーナ社(Cassina)
*1:ビトラ(Vitra)社(本社はスイスのバーゼルにあり1934年に創設。オフィス家具を中心に世界中に市場を広げるデザインマネジメントが卓抜な企業)は50年代からアメリカのハーマンミラー社とライセンス契約によりヨーロッパでイームズやネルソンの家具を「ビトラ・クラシック」として製造・販売。フランク・ゲイリー設計の「椅子の美術館」を持つことでも有名。尚、ベリーニ・コレクションは同社の開発責任者エゴン・ブロウニング(Egon Brauning)の力が大きい。

「人」との関わりから生まれる椅子
「梱包」をテーマとするアーティスト、クリスト(*3)が巨大なビルを布で包む。アートだとしても考えられない発想。
ベリーニは鉄のフレームを革で包んで椅子にする。それも四本脚の椅子に。これも私などには絶対に出てこない発想である。
「キャブ」に出会って、ありふれた素材でも加工方法によって信じられないモノになることを知ったのだが、鉄のフレームを革で包むことは先端的な科学技術でもなく「職人の技」である。驚いたのは職人の技による可能性を知らなかっただけで、これぞ最近よくいわれる「現場主義」の重要性とでもいえばよいのだろうか。
これまで数え切れないぐらい家具の製作現場を見てきたにもかかわらず。一般的な素材である木でさえも知らないことが多い。多すぎる。最近、ある工場を見せてもらったが、機械や科学技術の発展により思いもかけないことの可能性に驚くばかりである。
だが、なんといっても家具づくりに関わる最も重要な要素は「人」である。製作現場ではまだまだ手作業によるところが多く、生産段階に入ってからも関わる人の感性が製品の質を左右する。ウエグナーがデザインにより持ち込む工場を選んだように、家具は工場の「人と設備」、さらにトップの考え方(理念)により生まれるものが異なるから厄介だ。
「キャブ」によく出会ったのは20年以上も昔になるが、京都・祇園にこれも普通の発想にない変わったバーというかスナックがあった。通常より高い天井高で、その壁と天井はなんの装飾もなく白のプラスター塗りでただの真っ白。カウンターは少し幅の広い黒の大理石で、椅子は黒の「キャブ」が8脚ぐらいであっただろうか。そのころの商空間としてはありえないようなシンプルさ。バックの棚に活けられた赤い一輪の薔薇がなんとも映える空間であった。その上、ママは最初と最後の挨拶ぐらいで必要以上のことはしゃべらない変わった店であった。人と話し込みたいときにはこのことがかえって具合よく、「キャブ」によく腰をおろしたものだ。が、この店は「客を選ぶ店」といってよかった。「キャブ」もセールストークのいらないアイデンティティのある椅子。イタリアならではの職人の「技」とデザイナーの「発想」がみごとに結実したたぐいまれな一脚である。
ベリーニは新たな発想と卓越した造形力で現在も活躍する国際的なスターデザイナーであるが、スターにありがちな「人」とのかかわりを惜しんだデザイナーではない。「キャブ」は職人とのコミュニケーションなくしてモノにならなかったことは当然としても、ビトラ社の「ベリーニ・コレクション」では、同社の主任技術者エゴン・ブロウニングとの共同作業から生まれたといってよいほど企画段階からお互いに意見を交換しながら開発を進めた、と同社の社長・ロルフ・フェルバムは言う。(*4)
今日、広く市場に出る椅子はリートフェルトのようにデザイナーが自らの手でつくれるものではない。さらに、生産段階に入ってからでも、プラスティックの成型品のように製造され始めればどこまでも均一なものが生まれるわけではない。椅子が世に出るまでには企画から市場に出るまでの過程で多くの人の知恵や技術と感性が深くかかわり、その完成度を左右する。
「キャブ」と「ベリーニ・コレクション」。手づくりとメカニズムを内蔵した両極端のモノづくり。そのいずれにおいても、発想から製造までにかかわる人とのコミュニケーションの重要性はいうまでもない。が、家具づくりにはまだまだ現場に隠れた知恵や発想の源があることも確かであろう。
*2:人間工学に基づくメカニズムを内部に包み込みながら外からは一切感じさせず、背、座及びベルト部分の3ヶ所の布地が変えられるようになっていて、布や革によるバリエーションは340通りにもなるという。80年代初頭の同種の椅子は外観がプラスティックのシェルで構成されていてハードな印象であったが、そのイメージを一新した。また、スティールパイプの脚がついたサイドチェアまでシリーズ構成されている。
*3:クリスト(Christo,1935 〜)は妻のジャンヌ=クロードとともに「梱包」というテーマで巨大な建物から海岸の岩場などを布で包んだり、渓谷に布を張り巡らした作品を発表。ニューヨークを拠点に活躍する20世紀を代表するアーティスト。
*4:雑誌『AXIS』28号、1988 102 〜103頁